“歪み”サウンドが生まれる仕組みとは?
では、“歪み”サウンドは、どのように生まれるのか。
その仕組みを知っていると、より能動的に音作りが出来るようになります。
その仕組みを一言で説明するなら、『音割れ』です。
街角演説とか、構内放送とか。
出力の小さい音響システムで、音量足りなくてボリュームをどんどん上げていって…、
「ガガガ…バババ…」って具合に、音が割れた感じの声になる。
あれと同じことが、ギターアンプでも起こり、“歪み”サウンドが生まれます。
その仕組みを図解してみましょう。

上図の赤い波形は、
ギターのPU(ピックアップ)から出力され、アンプへ送られた音の(電気)信号を表しています。
入力された信号の大きさ(上下の幅)が、アンプのキャパシティを超えない範囲では、アンプからはクリーントーンが出力されます。
ここで!
入力レベルを、ググっと大きくしてやるとどうなるのか?
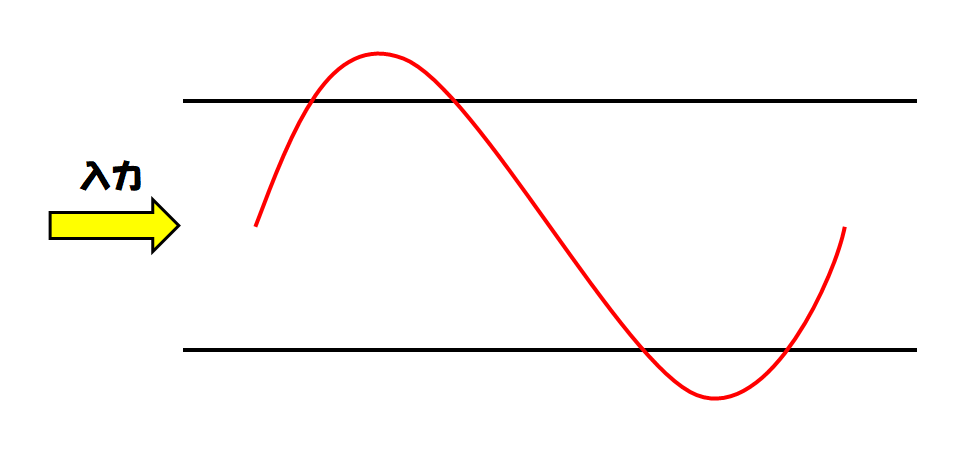
アンプのキャパシティを超えるくらい、信号の入力を大きくした状態ですね(過大入力)。
この時、出力される波形はどのような形になるのかというと・・。

そう、こんな感じで、
キャパオーバーした部分が押しつぶされたような、歪んで角ばった形の波形に変化するんです!
この波形が、“歪んだ音”の波形の基本的な形です。
しかし、
上の図のような角ばった形の波形は、実際に音を聴くと、
カリカリ・キリキリするような・・。
単なる音割れと言ってもいいような、
とても耳障りな音色、不快な音色になります。
でも、
私たちが普段耳にする“歪み”サウンドは、そんな耳障りな音色ではありませんよね?
なぜ、
エレキギターの“歪み”サウンドは耳障りではなく、むしろ心地よくも迫力のあるサウンドなのか!?
その秘密は、今や日常生活では見かけることの少ない、
真空管(チューブ)にあります。
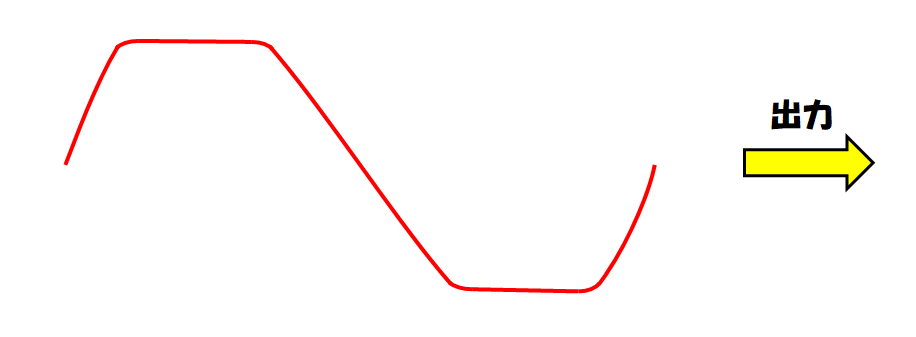
真空管アンプの場合、過大入力で波形が押しつぶされた際、
その角が滑らかに丸まったような形になります。
この状態が、耳障りにならない“歪み”サウンドです。
真空管アンプだと、歪み以外の要素でも、波形に角がたたず、
滑らかな状態で出力されます。
そのために、
真空管アンプのサウンドは、滑らかでウォームなサウンドなのです。
ギターアンプに関して、いまだに真空管のものが主流な理由は、そのサウンドがとても心地よくて音楽的だからなのでしょう。
ちなみに、
“Gain”と“(Master)Volume”の2つのツマミが付いているアンプでは・・、
“Gain” → 上図の入力の大きさを調整
“Volume” → 上図の出力の大きさを調整
・・というような役割になり、
歪み量(波形の歪み具合)を自由度が高く調整できるわけです。

次回は・・
さて、如何だったでしょうか?
今回は“歪み”サウンドの仕組みについて書きましたが。
この、アンプのナチュラル・ドライブによる波形の歪みを、小さな箱の中で再現したのが、
『歪み系エフェクター』です。
次回は、
歪み系エフェクターの種類について書いていきます。
では、今回はこの辺で!
by Akimaru






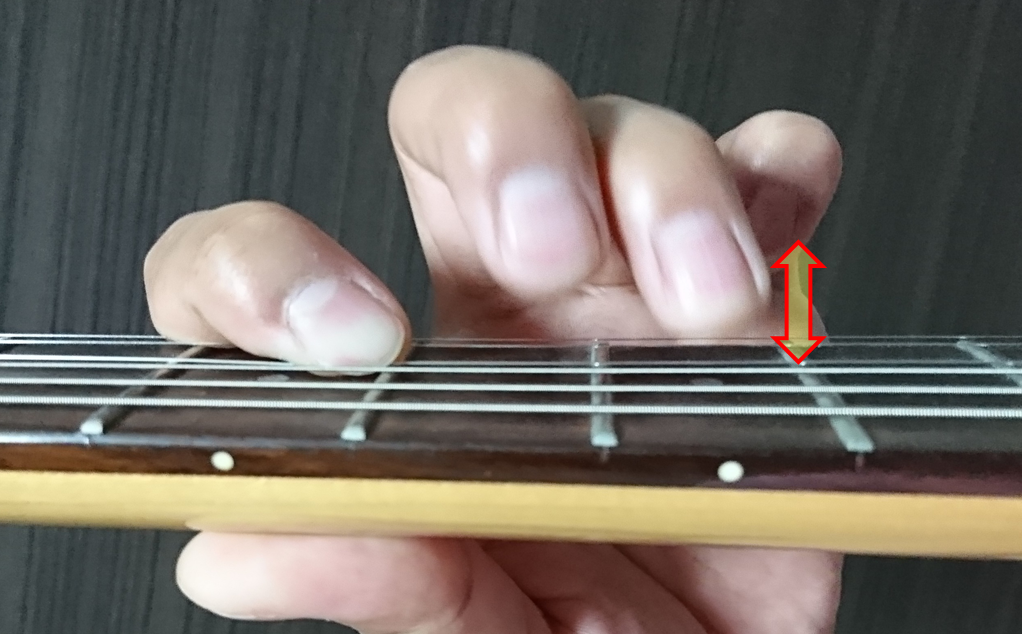






コメントを残す